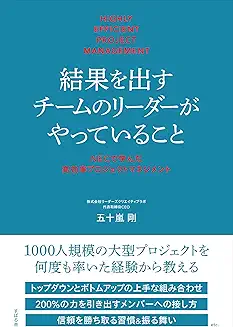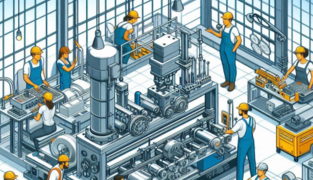【要約】
こちらの記事は『二兎を追う「両利きの経営」で8期連続増収増益、ダイキンはなぜ「深化と探索の両立」を実現できたのか?』の要約です。
◎ 二兎戦略とは?
- 経営における「トレードオフ(二者択一)」の常識に対抗する考え方。
- 通常、一方に集中する「一兎戦略」が提案されるが、資源と成果の関係が逓減する(成果が投入に比例せず鈍化する)場合、二兎戦略(両立)が合理的とされる。
- トレードオフの本質は、目的ごとの能力・組織・文化の違いによって生じる。
◎ 一兎戦略が有効な場合
- 目的が自己強化的で、一度追求を始めると変更しにくくなる場合。
- 異なる目的に適した組織や能力がまったく異なるため、リソースの分散が非効率になる場合。
◎ ダイキンの事例:「深化と探索の両立」
- 既存事業(空調)の深化と、新技術・新事業の探索を両立。
- 2015年、技術開発拠点「TIC(テクノロジー・イノベーションセンター)」を設立。700人の技術者を配置。
- 「構造的両利き」:深化と探索それぞれに特化したユニットを組織内に持ち、同時進行。
- 特徴的なのは、「人材の意図的な衝突」を活かすマネジメント。
- 探索型と深化型の人材を混在させ、議論や対立から創造的な解決を生み出す。
- 所長・副所長など、マネジメントも対照的な背景を持つ人材で構成。
- トップの井上礼之氏(元会長)が人事戦略を通じてこのバランスを設計。衝突を予見しつつ人材配置を行っていた。
◎ 成功の鍵
- 探索部門が既存部門から干渉・抵抗を受けないように経営トップが調整。
- 「ぶつかり合い」から創造性を引き出す文化と仕組みがある。
- ダイキンは空調事業の安定収益を活かしつつ、新たな挑戦にも踏み出している。
■ まとめ:
ダイキンは「深化と探索」という対立する目的を、組織的・人材的に両立する体制(構造的両利き)を築くことで、二兎を追う経営に成功しています。これは、トップの明確なビジョンと、意図的な人事戦略が可能にしたものです。
更に詳しい記事を読みたい方はこちら
【所感】
・「ぶつかり合い」というと回避したいと考えがちだが、それを創造性を引き出す文化と仕組みに変えたダイキンの戦略は素直にすごいと思う。