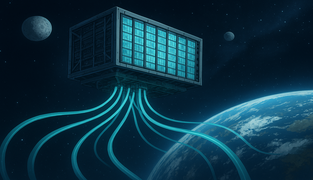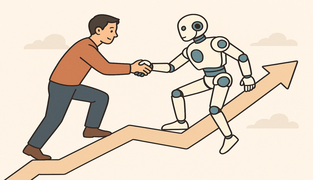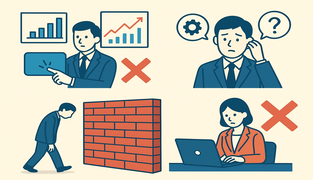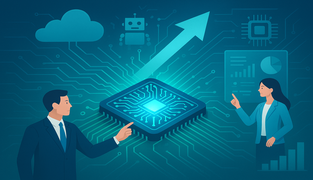 ニュース/ブログ
ニュース/ブログ 【要約】東京エレクトロンの「Epsira」とは何か?2030年の半導体技術に向けてDXを推進 — MONOist
2026.1.28 ◆半導体市場はICT(情報通信技術)の普及によって爆発的な伸びを続けて来た。IoT(モノのインターネット)やクラウドコンピューティングが注目されたことによる第1期の市場成長の波から始まり、現在はAI(人工知能)や自動運転技術、AR(拡張現実)/VR(仮想現実)などが市場をけん引する第2期の波が到来している。松島氏は「2030年には半導体市場規模が1兆ドル、日本円に換算すると150兆円に達すると試算されている。この市場規模の内、半導体製造装置市場に関しては全体の約10~15%を占めている」と語る。