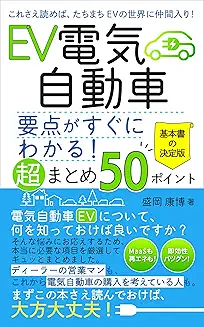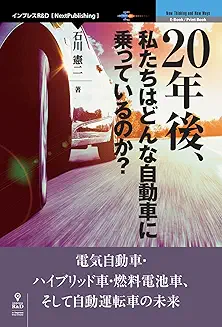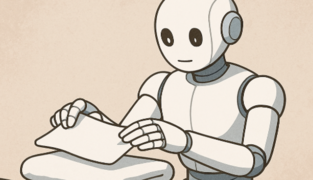【要約】
こちらの記事は『販売好調な「PHEV」を積極的に開発するメーカーと消極的なメーカー、方針が大きく分かれる理由とは?』の要約です。
PHEV市場の現状
- 2024年、BEV(純電気自動車)の販売が鈍化する一方で、PHEVは急成長。
- 世界初の量産型PHEVは2008年のBYD「F3DM」。
- 現在、BYDはBEVとPHEVに経営資源を集中し、秦PLUSシリーズが世界一の販売台数を記録。
PHEVに消極的なメーカーがある理由(5点)
- 中継ぎ技術と捉えている
最終的にはBEV/FCEVに移行すると見込み、PHEVは一時的存在と判断。 - 開発優先度の低さ
HEVやBEVの開発に比べてレイアウトが複雑・コスト高。 - 採算性(VFM)の問題
バッテリー大型化でBEVに近づき、中国勢との価格競争に不利。 - 環境規制への別解
米欧の規制はBEVやFCEVで対応可能と考えている。 - 実走行でのCO₂削減効果への疑問
EV走行頻度が低く、期待ほど環境効果が出ていない。
将来動向のポイント
- ユーティリティファクター(UF)見直し
EV走行割合基準が厳しくなればPHEV価値低下。 - エンジン熱効率競争
BYDが46%達成、他社も高効率化へ。 - EREV(レンジエクステンダーEV)の拡大
中国市場で急成長、PHEVとの区別が進む可能性。 - HEVからPHEVへのシフト
特にBYDが低価格戦略で新興国にも普及を狙う。日系メーカーは対応の遅れが懸念。
まとめ
- PHEVは一部メーカーにとっては重要戦略の柱だが、他社にとってはBEVへの過渡期的存在。
- 技術競争・規制・市場動向によって、今後数年で勢力図が大きく変わる可能性が高い。
- 特に日系メーカーはPHEVラインナップの拡充が急務。
更に詳しい記事を読みたい方はこちら
【所感】
・各国がEV車を作るのは環境の問題よりも別な戦略があるためだと感じる。EVにおいては海外に比べると劣勢に置かれている日本企業は海外企業に負けないような戦略・方向性を持って挑んでほしい。