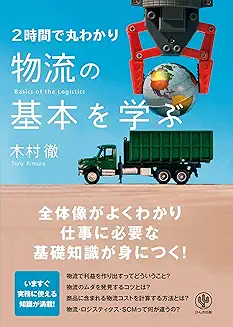【要約】
こちらの記事は『ヤマトと富士通、最強タッグがデータ連携で目指す先は?』の要約です。
◎ 背景と目的
ヤマトグループが設立した「Sustainable Shared Transport(SST)」は、持続可能な物流を目指し、幹線輸送の定時運行ネットワーク「SST便」を全国展開中。2025年3月現在、18路線運行中で、2025年度内に40路線に拡大予定。
◎ 物流効率とドライバー負担軽減
- ドライバー交代制による「日帰り運行」で労働環境を改善
- 幹線輸送を大手運送業者が担い、域内配送を地域企業が担うことで、地域活性化と分業体制を実現
◎ 富士通との協業と技術連携
富士通と共同でサプライチェーンのデータ連携基盤を構築。技術的特徴は以下の3点:
- 最適な輸配送計画作成(Fujitsu Unified Logistics活用)
- 標準ガイドライン準拠のデータ連携
- ブロックチェーンによるセキュアな情報管理
◎ ビジネスモデルと将来展望
- ヤマトグループの荷物を活用し、初期の積載率を補完
- 将来的にはAIも活用し、デジタルマッチングと効率化を推進
- 地域運送事業者と協力し、全国規模のネットワーク拡大を目指す
- 2027年度の黒字化、2040年までに業界横断型プラットフォームとの統合も視野
◎ 「フィジカルインターネット」の挑戦
- 社会課題(人手不足・環境負荷・少子高齢化など)の解決に向け、理想論とされる「フィジカルインターネット」を現実のビジネスとして構築中
更に詳しい記事を読みたい方はこちら
【所感】
・物流業界では、人手不足、労働環境の悪化、燃料費の高騰、2024年問題(トラックドライバーの時間外労働の上限規制)、2030年問題(さらに深刻な人手不足と脱炭素化への対応)など、多くの課題に直面しているので、こういった新たなビジネスモデルを構築し社会問題を解決していくことが大切だと思う。